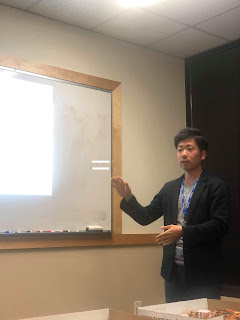今回JABIはJapan Bio Community(JBC)と共同で、「日米のバイオインキュベーター事情」をテーマとしたジョイントフォーラムを開催いたしました。内容は3名のバイオプロフェッショナルによる講演と、パネルディスカッションパートに分かれております。
◆講演パート
「アントレプレナー教育と神戸のバイオインキュベーターを利用したバイオ分野における大学発ベンチャー例」森一郎さん(神戸大学科学技術イノベーション研究科)
 |
| 森先生の講演 |
神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科は2016年に設置された。「バイオプロダクション」「先端IT」「先端膜工学」「先端医療学」の4つの理系専門分野の大学院生に、研究に加えて、その研究成果を事業化するたの事業・財務・知財戦略を学ぶ「アントレプレナーシップ分野」から構成されている。特にアントレプレナーシップ分野は、科学技術とイノベーションアイディア、アイディアとストラテジーなど、アントレプレナーの活動段階におけるギャップを埋めることを目的としていて、博士課程では博士論文の一部として詳細な事業計画を提出させている。
神戸市は、震災からの復興を目的とし医療都市構想を掲げており、神戸の一部区域を住居無しの研究や臨床施設のみに指定している。区域内は北からメディカルクラスター、バイオクラスター、シミュレーションクラスターの3つに分かれており、iPS細胞、アルツハイマー病の研究、医療用ロボットの開発などが行われている。神戸大学はその中で地域のエコシステムを作るミッションを担っている。現在では、基礎研究(研究機関)、臨床(病院)、産業化(企業、360社)が連携してエコシステムを形成し、雇用を11,000人創出している。例えば、域内の神戸医療イノベーションセンターには、神戸大学発のベンチャー企業が複数入居している。ゲノム編集技術を開発しているBioPalette、DNA合成技術を開発しているSynplogenなどがそうだ。
 |
| 広々としたオープンな会場 |
「MBC Biolabの紹介とイノベーションをサポートするパートナーシップの役割」神村洋介さん(Nitto Innovations)
2018年、日東電工はMBC biolabsとパートナーシップを締結した。MBC Biolabsは、大学発研究成果の商業化促進を目的としてUCSF, UC Berkeley, UC Santa Cruzの三大学が2000年に立ち上げたNPO法人『qb3』を前身として始まった。当時UCSF職員だったDouglas Crawfordは,qb3の活動の一環として,学内の空き実験室をスタートアップ向けのインキュベーター 『qb3 garage』として解放してみた.すると瞬く間に応募が殺到。直後に$数十Mの資金調達に成功するスタートアップも現れた。
また、2009年にDouglasら一部qb3職員でventure capital 『Mission Bay Capital』を立ち上げ,主にqb3発のスタートアップに投資を行い,これも成功を収める.しかし折からのリーマンショック不況によりqb3予算が削減され,インキュベーターの拡大が思うように進まなかった.そこでDouglasは2013年に大学から独立して『MBC Biolabs』をサンフランシスコMission Bayに設立.現在,San Carlosで大々的にインキュベーター施設を拡大しており,インキュベーター×投資モデルの成功例として注目を集めている.
スタートアップがインキュベーターを使うメリットは以下の通り。
1. Low cost:物件を探したり実験機器を用意したりするだけで、スタートアップは莫大な時間とお金を費やすことになってしまう。インキュベーターを利用することにより、割安で実験環境を手にすることができる。
2. Reputation:2013年から累計$3.5Bの資金調達に成功、エグジットも5社出ており環境がいい。現在約80社が加入しており、うち8割が創薬、2割がメドテック、わずかにフードテック、アグリテックなどの内訳となっている。さらに毎月5-10社が加入のためピッチに来ている。
質問:どんな人材が訪れているのか?
大学院卒、薬事や医療の社会経験あり、連続起業家が同じくらいの比率で来ている。
質問:大きい会社はどのようにかかわっていくのがよいか?
スポンサー料を払うことで、MBCが主催するスタートアップのピッチに参加、いち早くスタートアップとのコネクションを創れる。また、スポンサーのグレードによっては自社でピッチイベントを開催することもできる。その他実験機器の提供、場所の提供などで先行投資をしたり、コンサルに入ったりする機会もある。
質問:スタートアップの選抜基準はある?
インキュベーターに入る基準自体は投資基準と比べれば全然緩い。大きい問題に対してトライしている。それを実行するに足りる人材がいるか。約1年耐えられる資金力があるか。
 |
| 熱心に傍聴する参加者 |
「LA BioLabsの紹介と創薬ベンチャースタートアップ企業側の観点から」二村晶子さん(Hinge Therapeutics・JABI前会長)
Hinge Therapeuticsでは低分子医薬品の研究開発を行っており、特に最近は血友病の患者さんに対するソリューションを研究している。
今後BioLabs at LA BioMedというインキュベーション施設に入る予定。周辺のLAの北部に少し、San Diegoには多くのインキュベーション施設が存在する中で、二村さんが住んでいる、オレンジカウンティやLA南部にはまだほとんどそういった施設がない。しかし2028年のオリンピック開催に向けてLAは都市開発に大変力を入れている。LA南部トーランス(Torrance)にあるLA BioMedと、隣のUCLAの関連病院を中心にバイオメディカル分野中心のキャンパスの建設を進めており、今後こういった施設は増加していく見込み。
二村さんの会社はSouth San FranciscoのJLABSに入っていたこともあり、LAとベイエリアのインキュベーション環境の違いを感じる。以下がその相違を二村さんの視点からまとめたもの。
・LAの利点
地元のサポートが厚い。ちょっとしたリリースでもすぐ地元紙に掲載してくれるなど。
病院・患者へのアクセスが良い。実際にLA BioMedも病院に隣接しており、連携がとりやすい。
ベイエリアと比較すると人件費が安くすみ、人材の定着率も高い。
ハリウッドなど多くの人にアピールできる環境がある。
オリンピック開催に合わせ、スタートアップへの投資が強化されている。
・ベイエリアの利点
投資家へのアクセスが良い。実際にJLABSでも、入居者だけが利用できる1対1のコンサルシステムがあり、著名な投資家の時間をもらえた。
他スタートアップとのコラボレーション環境が整っている。
人材の層が厚い。
◆パネルディスカッションパート
 |
| 階段までいっぱいとなる盛況ぶりでした |
- インキュベーター選出で注意していることは?
森さん:施設に既に入居しているスタートアップと企業とのシナジーをみている。
神村さん:大きい問題にトライしていること、人材が揃っていること。いくらお金を持っていても、この点がないとだめ。
- インキュベーターを探している時の基準は?
二村さん:以前のベイエリアでは大手製薬企業とのコネクションをみていた。南に移ってからは、どういう投資家がそのインキュベーターに注目しているか、どんな設備が使えるかを重視している。
- 所属企業の中のコミュニケーション活性化のためにしていることは?
神村さん:ハッピーアワーなどは行っているが、基本的に会社同士のコラボレーションには強く関与しない。
二村さん:施設内にいる企業同士で話していたりすると、コラボレーションの話に繋がったりすることは多い。実際に動こうとしている案件もいくつかある。
- 現在所属しているインキュベーター、大学などで独自の取り組みをしていることは?
二村さん:施設の隣が病院なので、何かできそうだと思っている。
森さん:神戸にも医療エリアあるので、病院とも連携している。
- スタートアップの資金調達サポートはどのようにしているのか?
神村さん:もともと自己資金がある人が多い。あとはアイディアだけには投資できないので、少しでも証拠となるものが欲しい。
森さん:神戸大学発ベンチャーに対しては、海外から資金調達できるレベルのしっかりした特許戦略面、特許取得の支援を神戸大学で行っているケースもある。
- スタートアップの成果を見るための時間軸は、1年くらいなのか?
神村さん:MBCは基本1年半。でもそこは人間関係で伸びたりもしている。
二村さん:ジョンソンエンドジョンソン(JLABS)の場合は基本2年。それを過ぎても、いてほしい人にはいてもらう。一方いてほしくない人には不動産を紹介したり(笑)
- スタートアップの数に対しインキュベーターの数は十分か?
神村さん:足りていないと思っている。そのため、MBCもサンカルロスで40-50社入れる規模の建物をいくつも建てようとしている。不動産のアレキサンドリアも最近インキュベーション事業を始めた。新興VCはインキュベーターを利用したほうがいい。
森さん:神戸(日本国内)では民間発のインキュベーターはまだ見当たらない。ほとんどが、中小機構や県、市などが施設を作り入居者を募集している。
- バイオの人材集めはどのようにしているのか?
森さん:日本だと関東より関西の方がバイオ人の流動性が高いと言われている。
- インキュベーションラボで危険物を扱っていないかはどのように管理しているのか?
神村さん:危険な菌などを使っているところは、共用ラボではなく自社専用スペースの使用をお願いしている。
- 日本のバイオベンチャーはもっと成功するか?
森さん:投資の受け方次第だと思う。アメリカの方が投資を受けるチャンスが多く投資規模も大きい。。日本のCEOは研究肌で、ビジネスに弱い人多い。さらに、大企業からベンチャーに行きたがらない。
神村さん:研究ではなく経験の問題では?研究者とコンサルの比率が、日本とアメリカで全然違う。
◆筆者所感
特にバイオ分野におけるスタートアップは専門性が高く、実験環境の整備や臨床施設との連携などの点において、インキュベーターを活用するメリットが大変大きいように感じます。特にアメリカにおいては今後もインキュベーターは増えていくことが想定されるため、スタートアップにとってはより良い環境が整っていくのではないかと思います。
今回JBCさんと共同で会を執り行わせて頂いたことで、バイオというテーマについて深く掘り下げることができたと感じています。日本からアメリカに進出を考えている、もしくはアメリカでバイオの取り組みを検討されているみなさんのお役に立てれば幸いです。
 |
| イベント後は近くのイタリアンで懇親会! |
筆者:久保田華凜(JABIボランティア)