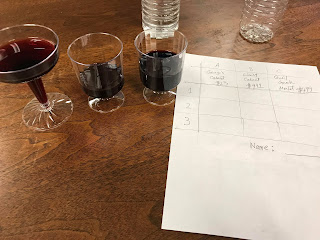2019年3月22日、ロボットの専門家2名でスペシャル座談会が行われました。
登壇者は、工学院大学Human Interface Lab准教授の見崎 大悟先生と、JABI会員であり長くロボット業界でビジネスをしているInnovation Matrix, Inc., CEOの大永 英明氏です。
Stanford大学Center for Design Researchにおいて、d.schoolをもちいた工学教育やイノベーション創生に関しての研究をおこなっていた工学院大学見崎大悟准教授 (Human Interface Lab)と、日米ロボット業界一筋40年余りのシリコンバレー在住の大永英明氏(Innovation Matrix, Inc., CEO)による、これからの時代のロボット、ヒューマンインターフェイス、AIなどの話が盛り沢山で大いに白熱した座談会となりました。
登壇者略歴は以下の通りです。
●見崎 大悟准教授(工学院大学Human Interface Lab准教授)(以下敬称略)
工学院大学工学部機械システム工学科准教授.東京都立大学大学院工学系研究科機械工学専攻博士課程修了。2015年~2016年に,Stanford University, Center for Design Research ,Visiting Associate Professor 研究テーマ:マイクロマニピュレータ,ロボット,設計支援,デザイン思考,工学教育など
ロボットを研究するエンジニアとしてのベースは“問題発見と問題解決”である。現在はそれをどうやって他者に伝えるか、つまりデザイン思考について考えている。
●大永 英明氏(Innovation Matrix, Inc., CEO)(以下敬称略)
米国ロボットメーカーに勤めたベテラン。現在、物流ロボットに力をいれているロボット一筋人間。現在は fetch robotics社のサービス用ロボットの販売に尽力している。(物流倉庫などにおいてロボットに地図などを記憶させ、人手不足の解消を試案)
今回のJABIブログはお二人と、会場のゲストたちの白熱した議論をお届けしたく、イベントで行われた座談会の書き起こしでお届けしたいと思います。
対談内容
ー 見崎:
ロボットには“産業用ロボット”と“それ以外のロボット”がある。産業用ロボットはニーズが明確である。ニーズがクリアな産業用ロボットなどは日本が強い。それはなぜ?
ー 大永:
アメリカ人は新しいことを開拓するのが好きであり、ないものを生み出す力が日本よりも優れている。日本人は最終製品だけでなく、基本技術から精度を高めようとする”モノづくり”に優れている。その反面、良いものを作ろうとし、新たなものを生み出すのが苦手。
ー 見崎:
モノづくりはそれぞれのコンテキストがあってこそ始まる。開発の上でさまざまな違いが影響し、その一つとして文化の違いがある。今後日本がロボット業界にて生き残っていくためには、この日本の良さを守るべき?それともアメリカのように変化したほうが良い?
ー 大永:
アメリカの学生はアグレッシブであり、日本とは異なり、自分から行動していく傾向がある。これが3Dプリンターの登場により、容易に形にすることが可能となったため、アメリカのスタートアップも、ハードウェアの分野への参入が可能となった。これにより、アメリカと日本の立場は同等となったが、業務委託をする際、日本は高コストであるため、中国など、他国が利用されることが多い傾向にある。この傾向によって、日本は今後の身の振り方について、考えなければいけない。
ー 見崎:
過去の日本を振り返った際に、80年代には様々なものが生み出されたが、90年代は…?
大きなポイント;マインドセットのチェンジ、良いものを作ることは大切であるが、効率化を行うような思考となり、楽しむといった感情に由来する研究がなくなる傾向となってしまった。
90年代に関して、何か記憶に残る大きな出来事はあったか?
ー 大永:
特にはない。
ただ、画像処理などアメリカでは当たり前のことが、日本では少し遅れて当たり前となっていく。日本が生き残っていくためには、固定概念を破り、新たなことに挑戦していけるかどうかも重要である。
ー 見崎:
ロボットには3つの要素がある。①アームなどのメカ、②物をつかんだり離したりする動作(エンドエフェクタ)、③認識がある。②について、物の形状により、その行動は多様となり、複雑化されてしまうため、吸着などの手法が用いられた。
エンドエフェクタについてどのように考えるか?
ー 大永:
問題点は、物流の場面では品数の多さである。この多種多様な形状について、1台のロボットでコントロールすることができないことが問題点である。別のアプローチとして、四角の箱に入れるなど、形状を同一化するという考えもある。目的がつかむことであれば、その方針でも問題ないのではないかと考えられる。困難な問題に対するチャレンジと問題を解決することのバランスが重要である。
ー 見崎:
開発をしていく上で重要になってくるのは、経験や専門性である。また、見方を変えることがとても重要である。ロボットと人間の役割分担において、ロボットは高速で認識が早い、人間は柔軟性があるなど、固定観念にとらわれるのは良くない。学生など、未経験者の視点に対し、それについて教えるのではなく、さまざまな分野の専門家らが学生にいろいろ教えたその知識による様々な視点を共有する姿勢が大切である。
ー 大永:
新たなものを作る際、日本企業は、きっちりしたクオリティーが保証されなければ、製品リリースできない。一方、アメリカはある程度できれば、見切り発車し、何かあれば修正するという楽観的な考え方がある。このバランスが大切である。クオリティーはもちろん大切であるが、マーケットへのスピードも重要である。
ー 見崎:
ソフトウェアに関しては、ある程度のクオリティーでもとりあえずやってみるという姿勢がとても大切。一方ハードはそれができないと思われがちだが、その概念を少し崩すことにより、次の新たなロボット設計において、進歩があるのではないかと考えられる。
質疑応答
● ロボット開発者はロボットを大好きという方が多く、その思いと他者が求めるものを作るというバランスはどのようにとっているのか。
ー 見崎:
学生の間にロボットを好きだという気持ちだけではいけないということに気づくことが多い。ただ、その気持ちにいつ気付けるかということが大切である。世の中の役に立つこと、誰かのためになることを考えるように思考をシフトすることがポイントである。
● 誰かの役に立つかについて考える際に、どうやってそこにアプローチしていくのかについて、ロボットに基準があるのか。
ー 大永:
第一に安全基準である。スピード、衝突なども考えながら設計することが大切である。日本がアメリカより良いものを作るためには、ビジネスマインドの人と一緒に開発する必要がある。ビジネスを目的とした考えも必要である。
ー 見崎:
エンジニアにもビジネス志向が必要であると最近は言われている。しかし、エンジニアが好きなように開発する環境に慣れたらという意見もある。
ー Shirokuさん(参加者):
最近の課題として、どうやって“ロボットが好き”という気持ちを生かしてビジネスを行えるのかを試行中である。
● 日本の中で自動運転は必要か?
ー 参加者の多くが“必要”という意見であった。ただ自動運転だけでなく、それをUberなどと関連付け、生活の改善やいろいろな場面に生かすという考え方もある。
ー 大永:
若い方は車を買わない傾向にある。自動運転は、渋滞の改善や高齢者の生活の質の向上に生かせるのではないかと思う。
● 最近では、ネットショッピングなど外出する必要性が減少している傾向にある。そのような状況下においても、自動運転は必要だろうか。
ー 参加者の中から、外に出て購入することも大切であるという声があった。
● ロボットには3種あると考えられる。I robot(物として管理する)、アイアムマン(自らが中に入り、ロボット化する)、さらにサロゲート(自分は動かず、代わりに動いてもらう)である。ロボット好きの方はどういうものが好きなのか。また、日本で描かれるロボットは平和思考であるのに対し、アメリカでは危険的な描かれ方が多い。そこの違いが幼少期に受けたロボットへの感情に関連し、ロボットの開発に影響している部分があるのではないか。
ー 大永:
3種のパターン、いずれも好きである。また、その幼少期の影響というものはあると考えられる。アメリカでは、軍事的な部分が一番金銭の動きがあるため、そのような場面に用いられる傾向がある。日本は逆にその部分にお金がないため、このように根本に違いが出る。ただ、NASAなど商業用への転用をうまくアメリカは行っていることにも違いがある。
● 近年ではロボットを好きな学生も増え、また共存しようという考え方を持つ方も増え、敵視するという傾向は減ってきたのではないか。
ー 見崎:
そのデザインという部分に戻り、自動運転について話すと、根底にあるのは“人はなぜ移動するのか”というものがある。人が生きていくには他者に会うということが重要であり、自動運転は必要である。自動運転の開発において、安全性やユーザーの安心感など何を享受するかというもの大きなポイントである。
ー 大永:
自動運転が導入されることにより、Uberやtaxi運転手など雇用に関わってくる。その労働者の時間についても改善が可能になるのではないかと考えられる。
● ロボットについて考えた際、なんでもできるロボットにするのか、単機能のほうがいいのか、どっちのほうがいいのか。
ー 大永:
単機能ではいけない、単機能であるとそれをしている時しか役に立たず、コストパフォーマンスが良くない。消費者の視点で考えた際に、多機能であるほうが良いと考える。
● 日本人には一つを極めるという性質がある。その一つを極めるのではなく、全体としてのシステムを構築するような発想になるよう、その概念を変えるようにロボットのデザインにおいて教育するにはどのようにすればよいのか。
ー 見崎:
日本人には職人志向の方が多い。その思考がそもそもどこから生まれるのか、知ることが大切。アメリカでは、アポロ計画により、視野が広がった。日本にいるだけでは、全体を見るような思考には至らないことが多い。他国へ行くなどし、行動範囲を広げることで、視野を広げることが大切。
● 感情を機械で表す開発を行う際、どのようにすればよいか。
ー 見崎:
知識の中で、言語化されているものとされていないものがあり、感情というのはされていないものである。そのため、経験やノウハウの蓄積しかないように考えられる。そもそもコミュニケーションとは何なのか、人間間の関係性なども考える必要がある。
終わりに
ー 大永:
私にとってのロボットの定義は、ロボットが人間の欲望を満たしてくれるというような意味で、世の中にあるすべての基礎技術のことである。
ー 見崎:
基本はロボットが好きな人は思う存分ロボット作ったらいいと思う。その環境づくりについて、シリコンバレーなどを見て、それを日本に生かせればと思う。